3ー2 自然を守りながら、人々の生活を支える
- 2017年9月22日
- 読了時間: 4分
森と人の共存を呼び掛けたシーナカリン王妃とブミポン国王の足取りは、Hall of Inspiration にて学ぶことができます。

5.水を治める
ー水がないと人は生きていけない
博識で勤勉、多彩な才能で国民から愛されたブミポン国王。1986年に彼がタイの開発を始めた際、まず最初に力を入れたのが治水政策でした。
こちらが当時のタイの問題を写真で紹介したコーナーです。

具体的には、以下のような問題がありました。
画像にある、黄色い付箋を目で追ってください。雨が減る、森林破壊、表土流出、土砂崩れ、干ばつ、洪水、水質汚濁、マングローブの消失、津波、海岸の生態系の崩壊…。われわれ人間にとって皮肉なことに、これらの問題は、人口増加から始まり、それぞれ被害は地域(山・高地・平地・海岸)ごとに異なるのです。

こんな国土全土に及ぶ問題をどうやって、解決ししていったのでしょうか。
ブミポン国王は、数千にも及ぶプロジェクトを立ち上げ、【地図・鉛筆・カメラ・無線】を持って、自らあちこちを巡り歩いたそうです。(クリックすると拡大します。)
そして行った8つの政策は、今でもタイの自然と人々の暮らしを守っています。(スライド。)
☆山での治水政策
①人口雨・・・雨が少ない地域に、人口雨を降らす。そのためにヘリで化学物質を散布し雨雲を作る。
②ベチバー(インド原産のイネ科の多年生草本)・・・根が深く、強い性質であることから、急斜面においても保水効果と栄養貯蓄効果を期待できる。土砂崩れや表土流出を大幅に防ぐことができる。
☆高地での治水政策
③砂防ダム・・・雨季になると、乾いた小川や、わずかな凹みなどに、雨が流れ込み、氾濫してしまう。それを防ぐために、水の流れを和らげ、土砂が流れ込まないようにするダムを作る。
④ダム・・・乾季でも様々な用途で水が使えるように、大量の水をせき止めておく。
☆平地での治水政策
⑤通気装置・・・工場などから流れ込む汚染物質によって汚染された水が集まるところに、水車のようなものを建てる。それを回して、水中の酸素濃度を高くすると、微生物の働きが活発になり、低コストで水を浄化することができる。
⑥モンキーチーク・・・猿は餌を食べるときに、頬(チーク)にたっぷり蓄えて、徐々に飲み込み、消化していく。それを参考にし、水が溜まりやすく、洪水が起きやすい平地において、水を蓄えておく場所を何か所か作っておく。徐々に海に排水するようにすることで、市街地での洪水による被害を減らし、大量の水が海に流れ込むことも防ぐ。
☆海岸での治水政策
⑦酸性土壌の改善
津波などによって、塩分濃度が高くなってしまった土壌では、農業ができない。なので、そうした土地の塩分濃度を下げるために、大量の水をまき、次に日照りにさせるという作業を交互に繰り返すことで、固体となった塩を表面に浮き上がらせ除去することができる。土に栄養が戻るまで繰り返す。(江戸時代日本の入浜式塩田をイメージしてください。)
⑧マングローブの植林
海岸線にマングローブを植えることで、津波から人々を守り、海岸の生態系を維持することができる。
この治水政策は、Hall of Inspiration のメインの一つであるため、遊びながら学べるコーナーになっています。影をかざすとイラストが動き出すという面白い仕組みになっています…笑


6.都会に住む人に伝える
実はドイトゥンを後にしたのち、バンコク市内の大きなデパートで開かれた自然保護を呼びかけるイベントにも行ってきました。この企画に携わったドイトゥンのスタッフさんに、経緯を伺いました。
「どんなに地方において自然を守るための取り組みに力を入れていても、都会の人が無関心では意味がない。バンコク生まれでバンコク育ちの子供の多くが、自然をテレビでしか知らないような時代になっている。もちろん実際にドイトゥンまで足を運んでもらうのが1番だが、それが難しいなら、自然を都会に持ってくればいい!」
デパートでの展示会と聞いていたので、パネルがずらりと並んでいるような…ものを想像していましたが!なんのなんの!とってもクリエイティブな展示会でした。五感を使って、頭を使って学べるような工夫があちこちに施されていました。
実際に大勢の親子連れが集まっており、大盛況のように見えました。メインステージでは立ち見の人がいるほどでした。日本でこんな展示会がデパートで行われるとしたら、どのくらいの人が集まるのだろうか。そしてそもそもこんなクリエイティブなものになるのだろうか。中進国のパワーを感じました。

7.問題解決のためのカギ
私がHall of Inspirationにおいて最も心象に残ったのが、「問題解決のためのカギ」と題したこのリスト。開発の仕事に関わるひとたちに向けてのアドバイスとも言えます。

「一滴の水滴が水面に落ちたときに広がる波紋」のように、タイのロイヤルファミリーが始めた取り組みは、国家を救い、周辺地域も希望を与えています。

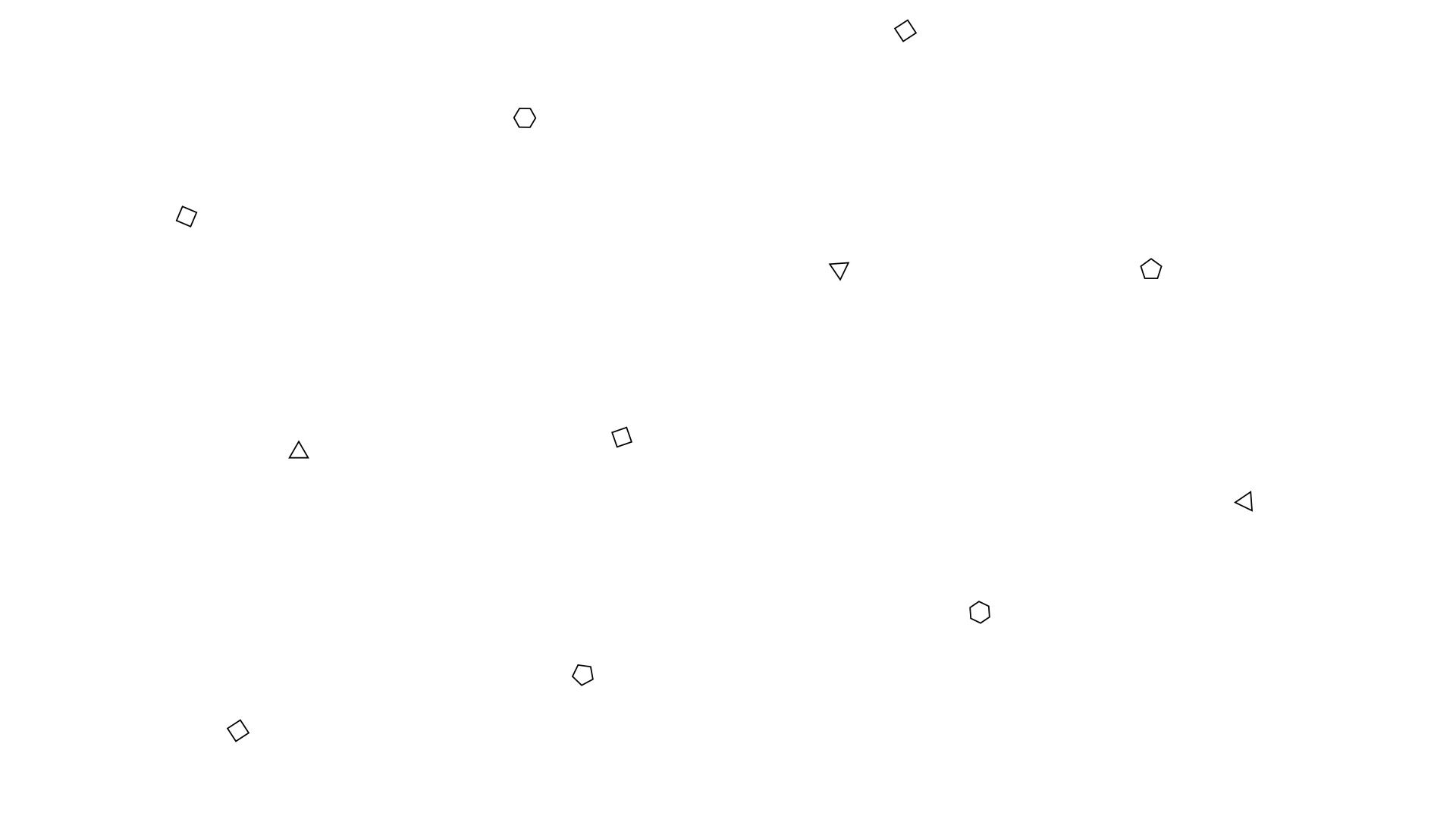




















































コメント